歯ぎしりの影響と対策|放置すると歯や身体に及ぶダメージとは?
- 2025年9月25日
- お口の病気
寝ている間や日中に無意識にしてしまう「歯ぎしり」。
ご自身では気づきにくいものですが、実は多くの方が悩まされている口腔習癖のひとつです。
「朝起きるとあごが疲れている」「歯がすり減っている気がする」「歯医者で歯ぎしりを指摘された」
など、歯ぎしりが体に与える悪影響は想像以上です。
今回は、歯ぎしりの原因・種類・放置することのリスク・そして歯科的な対策法について詳しく解説します。

目次
歯ぎしりとは?その種類と特徴
「歯ぎしり」と一口に言っても、実はいくつかのタイプがあります。
グラインディング(ギリギリ型)
最も一般的な歯ぎしりで、上下の歯をすり合わせるタイプ。
夜間にギリギリと音を立てることが多く、歯の摩耗やあごへの負担が大きいです。
クレンチング(くいしばり型)
音はしませんが、強く歯を噛みしめてしまうタイプ。
日中の集中時や緊張時、夜間の無意識下でも見られます。
タッピング(カチカチ型)
上下の歯を断続的に軽く打ち鳴らすように噛み合わせるタイプ。
他のタイプに比べて稀ですが、歯や顎関節へのダメージは無視できません。
歯ぎしりが起こる原因とは?
原因は一つではなく、複数の要因が絡み合って発生することが多いと考えられています。
ストレス・緊張
精神的ストレスや不安があると、無意識に筋肉が緊張しやすくなり、歯ぎしりが起こることがあります。
噛み合わせの異常
歯列の不正や補綴物の高さのズレがあると、不自然な噛み合わせがストレスとなり、歯ぎしりを引き起こすことがあります。
睡眠障害
睡眠時無呼吸症候群や睡眠の質の低下も、歯ぎしりの引き金となる場合があります。
習慣化
幼少期からのクセが残っている場合や、習慣として定着していることもあります。

歯ぎしりが引き起こす悪影響
歯の摩耗・破折
歯がこすり合わされることで、エナメル質が削れ、象牙質が露出し、知覚過敏や虫歯のリスクが増大。
ひどい場合には歯が割れたり、詰め物・被せ物が壊れることも。
顎関節への負担
過度な力が顎関節にかかり、顎関節症(あごの痛み・音・開けづらさ)の原因になることがあります。
筋肉・肩こり・頭痛
咀嚼筋の緊張が続くと、顔の筋肉や首・肩・頭にまで影響を与え、頭痛や肩こりを引き起こします。
審美性の低下
歯がすり減ることで歯の長さや形が変化し、笑顔の印象が変わってしまうことも。

歯ぎしりのセルフチェック
以下の項目に当てはまる場合、歯ぎしりの可能性があります。
◎起床時にあごが疲れている、痛む
◎歯が平らになってきた気がする
◎頬の内側に噛み跡がある
◎被せ物や詰め物がよく外れる
◎パートナーに歯ぎしりの音を指摘されたことがある
1つでも当てはまる場合は、歯科医院での診察をおすすめします。
歯ぎしりへの対策方法
マウスピース(ナイトガード)の装着
歯科医院で作る「ナイトガード」は、歯ぎしりによる歯やあごのダメージを軽減する装置です。
夜間の歯ぎしり時に歯同士が直接ぶつからないようにし、摩耗や筋肉への負担を緩和します。
※市販品もありますが、自分の歯に合ったオーダーメイドタイプの方が効果的で安心です。

噛み合わせの調整
詰め物や被せ物の高さ、歯列のズレによって歯ぎしりが生じている場合は、調整が必要です。
矯正治療で咬合バランスを整える場合もあります。
ストレスケア・生活習慣の見直し
十分な睡眠、リラックスできる時間の確保、カフェインやアルコールの摂取を控えるなど、日常生活でのストレス軽減も重要です。
ボトックス治療(必要な場合)
近年では、咬筋(こうきん)の過緊張を緩和するためにボツリヌス注射(ボトックス)を行うケースもあります。
一時的に筋肉の力を弱めることで、歯ぎしりのダメージを軽減します。
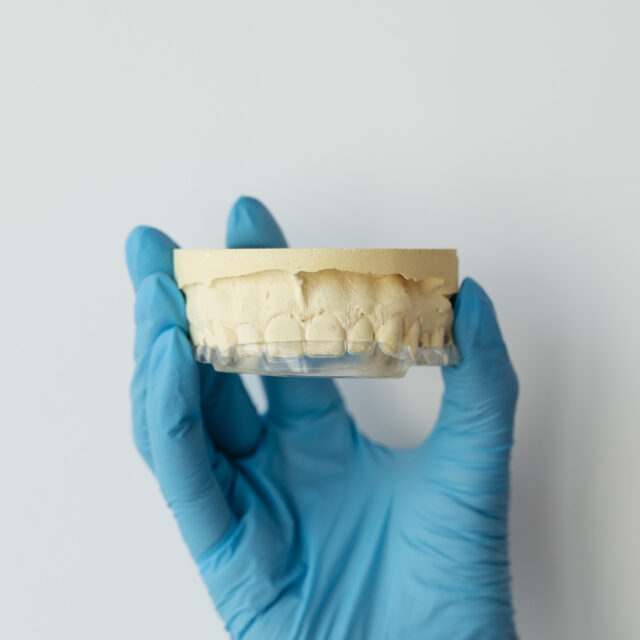
歯ぎしりを放置しないことが大切
歯ぎしりは自覚しにくく、「放っておいても大丈夫」と思われがちですが、そのままにすると歯・顎・身体全体に悪影響が及びます。
日中のくいしばりに気づいたときは意識的にリラックスし、歯を離す習慣をつけましょう。
また、歯科医院での定期的なチェックで、歯ぎしりの兆候や影響を早期に発見・対処できます。
まとめ
◎歯ぎしりは「ギリギリ」「くいしばり」「カチカチ」など複数のタイプがある
◎原因はストレス・噛み合わせ・習慣など複合的
◎放置すれば歯の摩耗・知覚過敏・顎関節症・頭痛などの原因に
◎対策は「ナイトガード」「咬合調整」「ストレスケア」など
◎自分では気づきにくいため、歯科での相談が重要
歯ぎしりの予防と対策には、ご自身の状態を知ること、そして早めの対応がカギです。
気になる症状がある方は、ぜひお気軽に歯科医院にご相談ください。


